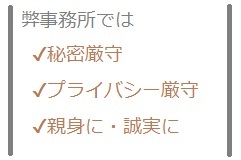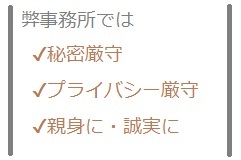|
| Q1.好きな人ができたので離婚したい!? |
| Q2.私や子供に暴力をふるう?! |
| Q3.相手が浮気をしているようだ? |
| Q4.熟年離婚を考えているのですが・・ |
| |
 |
| Q5.突然相手から離婚を迫られた?! |
| Q6.離婚する理由がないのに離婚できるの? |
| Q7.離婚したいが、離婚後の問題点は? |
| |
 |
| Q8.どのように進めたら良いのでしょうか? |
| Q9.相手が離婚に応じてくれないのですが・・・ |
| Q10.調停と裁判の違いは? |
| Q11.離婚したらすぐ再婚できますか? |
| |
 |
| Q12.離婚は合意したが、財産分与等で意見が対立 |
| Q13.財産分与できる財産とは? |
| Q14.不動産の分け方は? |
| Q15.年金は分けることができるの? |
| Q16.慰謝料を請求できるケースとは? |
| Q17.慰謝料の相場は? |
| Q18.慰謝料・財産分与の支払は分割OK? |
| Q19.浮気相手に慰謝料を請求できますか? |
| Q20.慰謝料や財産分与に税金はかかるの? |
| Q21.養育費の目安は? |
| Q22.20歳の大学生の養育費を請求できますか? |
| Q23.養育費を毎月確実に支払ってもらいたのですが |
| |
 |
| Q24.親権・監護権とは? |
| Q25.親権者が決まらないときは? |
| Q26.離婚すると子供に会えなくなるの? |
| Q27.母親が親権者の時、子供の戸籍はどうなるの? |
| Q28.子供の姓(苗字)を母親の姓にするには? |
| Q29.子供に別れた夫の相続権はあるの? |
| Q30.父親が親権者になることができるの? |
| |
 |
| Q31.離婚すると戸籍はどうなるの? |
| Q32.離婚届けの証人は誰でもいいの? |
| Q33.離婚すると旧姓に戻るの?現在の姓のままにするにはどうすればいい? |
| Q34.離婚届けは当事者が揃って提出するの? |
| Q35.自分の戸籍に子供を移すときの離婚届けの書き方は? |
| |
 |
| Q36.年金分割の手続きは離婚後にするの? |
| Q37.子供の戸籍を夫の戸籍から自分の戸籍に移すには? |
| Q38.親権者の私(母親)の姓は旧姓に戻し子供の姓は夫の姓を名のることはできるの? |
| Q39.母子家庭になった場合、生活支援の制度はあるの? |
| Q40.離婚後、しなければいけない手続きは? |
| Q41.約束したのに養育費が振り込まれない?! |
| Q42.離婚すると別れた夫の親族とは縁が切れるの? |
| Q43.離婚後、親権者の変更はできるの? |
| |
| Q1.好きな人ができたので離婚したい!? |
|
A.
不貞行為は離婚事由のひとつですが、離婚の原因をつくった側(有責配偶者)から離
婚を要求しても、相手が拒否すれば離婚は困難です。
長い期間別居していて、夫婦関係が破たんしている場合などは離婚請求が認められる
ことがあります。
戻る
|
| Q2.私や子供に暴力をふるう?! |
|
A.
DV(ドメスティック・バイオレンス:家庭内暴力)を受け、被害が大きい場合は、
すぐに関係機関(警察・DV相談センターなど)に相談しましょう。
自分や子供の安全確保のため、家をでることも考え、それから離婚調停を申し立てる
方が良いでしょう。
戻る
|
| Q3.相手が浮気をしているようだ? |
|
A.
浮気は裏切り行為であり、配偶者にも浮気相手にも慰謝料を請求することができま
す。
疑わしい行動が頻繁に見受けられたら、写真・映像・携帯電話の記録やメールなどの
証拠を入手します。
費用はかかりますが、良心的な調査会社に依頼するのも良いでしょう。
浮気を理由に慰謝料を請求し離婚をするならそれなりの準備が必要です。
戻る
|
| Q4.熟年離婚を考えているのですが・・ |
|
A.
夫の定年退職、子供達も一人前に巣立っていき、残りの人生を自由に生きていきたい
というのが熟年離婚の理由です。
ただ、相手が同意してくれれば良いのですが、具体的な離婚事由がなくただ「離婚し
たい」では、なかなか納得してもらえないようです。
時間をかけて準備し、裁判も辞さない覚悟で行動することが必要です。
財産分与や年金分割をしっかり考慮して、費用はかかりますが弁護士に相談すること
も考えましょう。
戻る
|
| Q5.突然相手から離婚を迫られた?! |
|
A.
難しいかもしれませんが、まず冷静になって相手の話を聞きましょう。
二人で話し合って、離婚を受け入れるのであれば条件等を協議していきます。
離婚を受け入れることができなければ、例えば、別居し距離を少し置くことを提案
するのも良いでしょう。
また、両親や友人・専門家に相談し、夫婦円満調整の調停を家庭裁判所に申し立て
ることも考えましょう。
相手が強硬に離婚を迫ってきて、勝手に離婚届を出してしまうような恐れがある場
合は、役所に離婚届不受理申出を提出しておきます。
戻る
|
| Q6.離婚する理由がないのに離婚できるの? |
|
A.
夫婦がお互いに離婚の意思があれば、離婚事由がなくても協議離婚できます。
しかし、片方が離婚を拒んでいる場合は、相手を納得させるしかありません。
なんとしても離婚したい場合は、最終的には裁判になりますが、法律で定める離婚
事由が必要です。
【民法第770条】
1.夫婦の一方は、次に揚げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
戻る
|
| Q7.離婚したいが、離婚後の問題点は? |
|
A.
離婚後の問題点としては、財産分与や慰謝料が約束通りに支払われない、
未成年の子供がいた場合には約束したのに毎月の養育費が振り込まれないケースが
あるようです。
やはり、離婚協議の際にきちんと協議書を作成し、公正証書にしておかれた方が良
いでしょう。
戻る
|
| Q8.どのように進めたら良いのでしょうか? |
|
A.
①お互いの離婚の意思を確認します。
②離婚に合意できない場合は、家庭裁判所へ(調停→裁判)
③離婚には合意するが、離婚条件(親権・財産分与等)に合意できない場合は、
家庭裁判所へ
→ 調停の成立、審判・判決が確定した場合、離婚届を作成し、離婚届を役所に
提出
④離婚の意思、離婚条件ともに合意できた場合は、離婚協議書の作成
⑤離婚協議書を公正証書にする。
⑥離婚届を作成
⑦離婚届を役所に提出
⑧年金分割する場合は最寄の年金事務所へ
戻る
|
| Q9.相手が離婚に応じてくれないのですが・・・ |
|
A.
相手が離婚に応じてくれないとき(協議離婚できないとき)、いきなり裁判を起こ
すことはできません。
調停前置主義といって、調停を経なえれば裁判に進むことができません。
調停はご自分で手続きし進めていくことも可能ですが、裁判となるとやはり弁護士
に依頼した方が良いでしょう。
裁判は相当な精神的に負担がかかり、費用もかかります。また、望み通りの判決が
でるとも限りません。
なんとか協議離婚する方法を考えていきたいものです。
戻る
|
| Q10.調停と裁判の違いは? |
|
A.
夫婦の話し合いにより離婚を決める(協議離婚)ことができない場合、家庭裁判所
の仲介で離婚が成立するのが調停離婚です。
調停は家庭裁判所の調停委員が双方の話を聞き、解決策を探っていき話し合いをま
とめます。
調停でお互いが合意すれば離婚が成立します。
裁判離婚は調停で話がまとまらず、それでもまだ離婚を望む場合は、家庭裁判所に
裁判の訴訟を起こします。
裁判ですから、民法に定める離婚事由が必要です。
調停前置主義といって、いきなり裁判を提起することはできません。必ず先に調停
を経ることが必要です。
戻る
|
| Q11.離婚したらすぐ再婚できますか? |
|
A.
男性の場合は、離婚届を役所に提出した翌日に婚姻届を提出しても受理されます。
女性の場合は、民法の規定により離婚から6カ月間は再婚ができません。
この規定は、離婚後に妊娠が判明した場合、父親は前の夫なのか、再婚相手なのかを
めぐりトラブルになることを防ぐためです。
戻る
|
| Q12.離婚は合意したが、財産分与等で意見が対立 |
|
A.
離婚には合意したが、財産分与の割合などお互いの欲が出て話がまとまらないケー
スがあります。
専門家や友人知人に間に入ってもらっても合意できない場合は、財産分与の調停を
家庭裁判所に申し立てることになります。
戻る
|
| Q13.財産分与できる財産とは? |
|
A.
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた共有の財産を公平に分けることです。
共有財産とは、夫婦で協力して購入、取得した土地、建物、自動車、有価証券、
高額な家財道具、美術品、宝飾品です。
住宅ローンや借金も財産分与の対象です。
財産分与の対象外の財産とは、夫婦それぞれの固有財産です。
例えば、嫁入り道具、遺産相続で得た財産、独身時代にためた預貯金や購入した
ものなどです。
戻る
|
| Q14.不動産の分け方は? |
|
A.
財産分与の割合は原則、総共有財産の1/2ずつです。
お互いの合意で割合は自由に決められます。
不動産の場合もたとえ夫名義になっていても共有財産です。
売却して現金で分配する方法が一番良いのですが、簡単にはいきません。
どちらか一方が住み続ける、住宅ローンが残っている等問題があります。
★特に住宅ローンが残っている場合で不動産もローンとも夫名義で妻が財産分与
として不動産を取得する場合は要注意です。
不動産の名義を妻に変更できないケースがほとんどです(金融機関が承諾しない)
ので、離婚後も元夫が住むことのない住宅のローンを支払っていくことになり
ます。
ローン完済後、名義を元妻に変更します。
このようなケースの場合、必ず離婚給付契約書を公正証書にしましょう。
戻る
|
| Q15.年金は分けることができるの? |
|
A.
厚生年金、共済年金に加入している方で、結婚して離婚するまでの期間、夫が受け
取る年金の1/2を限度に専業主婦だった妻が受け取ることができる制度です。共働き
のご夫婦も分割できます。
詳しくは、年金分割のページをご覧ください。
戻る
|
| Q16.慰謝料を請求できるケースとは? |
|
A.
慰謝料の請求できるケース
・相手の不貞(浮気)
・暴力行為
・同居の拒否、協力義務違反
・過度の飲酒・ギャンブル
・一方的な離婚要求
慰謝料の請求が認められないケース
・信仰上の対立
・性格の不一致
・有責行為がない
・相手側の親族との不和
戻る
|
| Q17.慰謝料の相場は? |
|
A.
・不貞行為(浮気・不倫)で100万~500万
・暴力行為で50万~500万
・性行為の拒否で0~100万
慰謝料を決める基準になる要素としては、苦痛の程度、期間、回数、婚姻期間、
有責者の経済状況、支払能力社会的地位などです。
戻る
|
| Q18.慰謝料・財産分与の支払は分割OK? |
|
A.
慰謝料や財産分与の話し合いがまとまったら支払方法・支払時期も話し合っておき
ます。
一括で支払うことができない場合は分割にしますが、必ず分割の回数や支払期間を
文書にしておきましょう。
分割にすると支払が滞る場合がありますので、公正証書を作成しておくと良いで
しょう。
戻る
|
| Q19.浮気相手に慰謝料を請求できますか? |
|
A.
慰謝料とは、相手の不当・違法な行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償
を意味します。
よって、配偶者の浮気相手にも請求できます。ただし、浮気相手が既婚者であるこ
とを知りながら関係をもった場合であることが要件です。
戻る
|
| Q20.慰謝料や財産分与に税金はかかるの? |
|
A.
現金の場合は原則、双方とも税金はかかりません。
ただし、社会通念上の限度を超えた高額を受けた場合は、超えた部分には贈与税が
課せられる場合があります。
また、不動産や株式などの有価証券には譲渡所得税が課せられる場合があります。
たとえば、夫が土地を相続した時の価格より大きく値上がりした状況で、財産分与
として妻に与える場合、
夫に譲渡所得税が課せられ、妻には、多すぎる分に対して贈与税が課せられます。
その他不動産の場合は、名義変更の際にかかる登録免許税、その後毎年、固定資産
税が課せられます。
戻る
|
| Q21.養育費の目安は? |
|
A.
未成年の子供にはお金がかかります。受け取る側は少しでも多く欲しい気持ちは
わかりますが、支払う側の経済状況も考慮しなければなりません。
養育費の目安としては、支払う側の年収が500万の場合子供の人数もよりますが、
子供1人で4万~6万円です。
戻る
|
| Q22.20歳の大学生の養育費を請求できますか? |
|
A.
「成人の子と暮らす親から他方の親に対しその子に対する扶養義務の分担を合意す
ることもできる」
上記を公証人に確認し、「大学を卒業するまで養育費を支払う」旨を記載した、
公正証書を作成しております。
戻る
|
| Q23.養育費を毎月確実に支払ってもらいたのですが |
|
A.
養育費に関しても離婚の合意内容として文書に残し、公正証書を作成しましょう。
公正証書には「強制執行認諾条項」を記載し、養育費の支払いが滞った場合は、
給料等を差し押さえて、強制的に支払を受けることができるようにすることが大切
です。
戻る
|
| Q24.親権・監護権とは? |
|
A.
離婚の際、未成年の子供がいる場合は必ず親権者を決めなければなりません。
協議しても決まらないときは調停を申し立てることになります。
親権とは、未成年の子供に対して親の責任や義務であると考えます。
子供の財産を管理し、法律行為や身分行為を代理します。
親権者とは別に監護権者を決めることができます。
監護権とは子供の住まいを決め、身の回りの世話・教育・しつけなどを行います。
例えば、父親が親権者となり、母親が監護権者になって子供を引き取り生活するこ
とも可能です。
戻る
|
| Q25.親権者が決まらないときは? |
|
A.
親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申立てます。
調停が不成立になると自動的に審判に移行されます。
家庭裁判所の調査官が事実調査をし審判官が親権者を指定します。
審判に不服がある場合は不服抗告を申し立てる必要があります。
高等裁判所で再審理を行い親権者を決定します。
戻る
|
| Q26.離婚すると子供に会えなくなるの? |
|
A.
別れた子供と会うことを面接交渉といいます。
子供に悪影響を与えてしまうような特別な理由がない限り子供に会うことができ
ます。
裁判所も面接交渉権を認めています。
離婚協議の中に面接交渉について取り決めておくと良いでしょう。
子供の福祉と利益を一番に考えて取りきめましょう。
戻る
|
| Q27.母親が親権者の時、子供の戸籍はどうなるの? |
|
A.
母親が親権者として離婚届を提出した場合、母親が従前の戸籍に戻る、あるいは
新しい戸籍を複製しても、子供の戸籍はそのままです。一般的には筆頭者が父親
の戸籍のままになります。当然、氏(苗字)も変わりません。
戻る
|
| Q28.子供の姓(苗字)を母親の姓にするには? |
|
A.
親権者を母親として離婚後新しい戸籍を複製します。
当然に母親の姓は旧姓に戻ります。
子供が15才未満の場合は母親が、15歳以上であれば子供自ら又は母親が
家庭裁判所に子供の氏の変更許可を申立てます。
許可を得たら、母親の戸籍に子供を入籍させます。
戻る
|
| Q29.子供に別れた夫の相続権はあるの? |
|
A.
親権者が母親であるからといって、子供と血縁関係が切れるわけではありません。
当然に元夫の相続権は子供にあります。
ただし、元夫の相続権は元妻にはありません。
戻る
|
| Q30.父親が親権者になることができるの? |
|
A.
夫婦の合意があれば、父親が親権者となることはできます。
ただ、協議で決まらなければ家庭裁判所に調停・審判を申立てます。
調停・審判でも決まらなければ、高等裁判所が決定します。
一般的に母親が親権者として決定することが多いようです。
戻る
|
| Q31.離婚すると戸籍はどうなるの? |
|
A.
一般的なご家庭の場合を例にしますと、夫が戸籍の筆頭者で妻と子供がいる場合で
子供の親権者を妻とする場合
離婚の際、妻は従前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を編製するかを選択し、離婚届を
提出
【夫が筆頭者である戸籍】
・妻が除籍されます。
・離婚の記載がされます。
・子供は変わらずそのままです。
【妻の戸籍】
・離婚届提出の際、従前の戸籍に戻るを選択していれば、従前(両親の戸籍が
一般的)戸籍に戻ります。
・離婚届提出の際、新しい戸籍を編製するを選択していれば、新たに妻が筆頭
者である戸籍が編製されます。
戻る
|
| Q32.離婚届けの証人は誰でもいいの? |
|
A.
証人は20歳以上であればどなたでも構いません。
証人になったからといってなにか責任や義務が生じることもありません。
戻る
|
| Q33.離婚すると旧姓に戻るの?現在の姓のままにするにはどうすればいい? |
|
A.
離婚届けの「離婚前の氏にもどる者の本籍」欄には何も記載しないで、「離婚の
際に称していた氏を称する届け」を離婚届けと同時に提出します。
そうすると旧氏に復氏せず(親の戸籍に戻らず)現在氏(姓)の新戸籍が編製
されます。
一旦「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出すると旧姓に戻すことは
困難になりますので、注意が必要です。
例えば、旧姓が「佐藤」で結婚して「山田」になり、離婚した際、「山田」のまま
で「佐々木」と再婚、その後離婚すると、旧姓は「山田」になります。
戻る
|
| Q34.離婚届けは当事者が揃って提出するの? |
|
A.
当事者お二人揃って提出する必要はありません。どちらか一方でも良いですし、
代理の方が使者として提出しても良いです。代理人への委任状も必要ありません。
ただし、窓口に来た方の本人確認(運転免許証等)の提示を求められます。
戻る
|
| Q35.自分の戸籍に子供を移すときの離婚届けの書き方は? |
|
A.
【母親が親権者となり子供を自分の戸籍に移す場合】
母親の新戸籍を編製し、子供を入籍させることになります。
離婚届けには親権者に母親を指定し、「妻が新しい戸籍をつくる」といった形で
離婚届けを作成します。
戻る
|
| Q36.年金分割の手続きは離婚後にするの? |
|
A.
年金分割の手続きは離婚後2年以内にしなければなりません。
詳細は年金分割のページをご覧ください。
戻る
|
| Q37.子供の戸籍を夫の戸籍から自分の戸籍に移すには? |
|
A.
【離婚から現在の姓のまま子供を自分の戸籍に入籍させるまでの流れ】
①「離婚届け」と「離婚の際に称していた氏を称する届け」を同時に役所へ
提出
②離婚が反映された書類を添付し、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」
を行う
③家庭裁判所からの変更を認める「審判書」を持参し、子供の入籍届けを役所
に提出
※上記のケース場合、子供の姓は変わらないのですが戸籍を移動させるために
家庭裁判所の許可が必要になります。
戻る
|
| Q38.親権者の私(母親)の姓は旧姓に戻し、子供の姓は夫の姓を名のることはできるの? |
|
A.
離婚届けに「妻はもとの戸籍に戻る」を記載すると復氏し、従前(親の戸籍)の
戸籍に戻ります。
子供はそのまま夫の戸籍に残り、当然に姓もそのままです。
ただ、親権者が母親であり、母子家庭になりますので、ひとり親家庭を支援する
制度等の手続きの際、支障がでできます。母親と子供は同一の戸籍であることが
求められます。
よって、子供の姓を変えたくなければ、母親は「離婚の際に称していた氏を称す
る届け」を提出し、新戸籍を編製後、子供を入籍させる手続きが必要になります。
戻る
|
| Q39.母子家庭になった場合、生活支援の制度はあるの? |
|
A.
ひとり親家庭が対象の支援制度で児童扶養手当と児童育成手当があります。
母子家庭だけではなく父子家庭でも利用できます。
所得制限等がありますので確認が必要です。
その他医療費助成や税金軽減制度などがあります。
戻る
|
| Q40.離婚後、しなければいけない手続きは? |
|
A.
離婚が成立(離婚届けを提出)後は、様々な手続きを行う必要があります。
・引っ越しする場合は住民票の変更
・健康保険や年金の手続き
・子供の氏の変更や戸籍の移動
・学校の転校の手続き
・子供手当、児童扶養手当等の手続き
・ひとり親家庭優遇制度の手続き
・身分証明書(運転免許証・パスポート等)の変更
・生命保険の名義変更
・財産分与で得た不動産や自動車、有価証券等の名義変更
・その他
戻る
|
| Q41.約束したのに養育費が振り込まれない?! |
|
A.
離婚時に約束事を文書に残してあるかどうかによります。
文書がない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる必要があります。
強制執行認諾条項付きの公正証書を作成していれば、まず内容証明郵便で養育費
の支払いの催告をします。
内容として、支払わなければ給料等の財産を差し押さえる旨を記載します。
その後何も連絡をしてこないような場合、強制執行(財産の差し押さえ)の手続き
に入ります。
戻る
|
| Q42.離婚すると別れた夫の親族とは縁が切れるの? |
|
A.
離婚と同時に配偶者ともその親族とも赤の他人になります。
ただ、子供にとっては祖父母であり、子供の利益を考慮して付き合っていくこと
になるでしょう。
戻る
|
| Q43.離婚後、親権者の変更はできるの? |
|
A.
親権者の変更は家庭裁判所に調停を申立て、許可を得なければなりません。
調停で決まらなければ審判に移行します。子供の福祉にかなうか、変更の必要性
など決定的な理由がなければ親権者の変更は難しいようです。
【親権者の変更が認めれれるケース】
・親権者が長期で入院・海外転勤
・子供へ暴力・虐待が行われている。
・育児放棄など養育環境が悪い
・子供が望んでいる
戻る
|